就労支援 利用体験談【はるかぜ通信第7号 パート6】
はるかぜ通信第7号パート6
はるかぜ利用体験エッセイ「転機」
ここでは、就労支援PGに通い、ステップアップをしていく具体的なイメージを持って頂けるように、就労支援PGに現在参加しているメンバーの利用体験談を紹介したいと思います。

就労支援PGメンバーのピノです。
僕は最初は診察ではるかぜクリニックに来て、そこからゆるやか就労を経て現在は午後の就労支援PGに参加しています。
①ゆるやか就労:主治医に言われて、最初は渋々……
僕が就労支援PGに参加したのは主治医に勧められたことがきっかけでした。
勧められた当初は正直気が進みませんでしたが、毎月診察のたびに言われているうちにだんだん断りづらくなって渋々了承した記憶があります。
最初は週4日通う自信がなかったので主治医と話し合い、週2日のゆるやか就労から始めることにしました。
何年も主治医と家族以外とはほぼ会話をしないような生活をしていたので、他人とコミュニケーションがとれるかがとても不安でした。
初日デイケア室に行った時のことをよく覚えています。
何をするのかもよく分からず不安な気持ちで教室に入ったのですが、入ってすぐ女性の参加者に話しかけられました。
彼女は周りの人に積極的に話しかけ、参加者が話しやすい雰囲気をつくっていました。
その雰囲気のおかげで自分でも驚くほど自然に周りの人たちと会話ができました。

その日の講座は写真立てを作るというもので、普段はやらないような作業に悪戦苦闘しながらもみんなで話をしたりして楽しんで参加できました。
初日の段階で続けていけそうだなと思いました。
ゆるやか就労ではみんなでコラージュ(貼り絵)を作ったり、絵しりとりをしたり大人になってからはなかなか経験できないようなことを体験できました。
特にコミュニケーションにおいて自信を深められたことが大きかったと感じます。
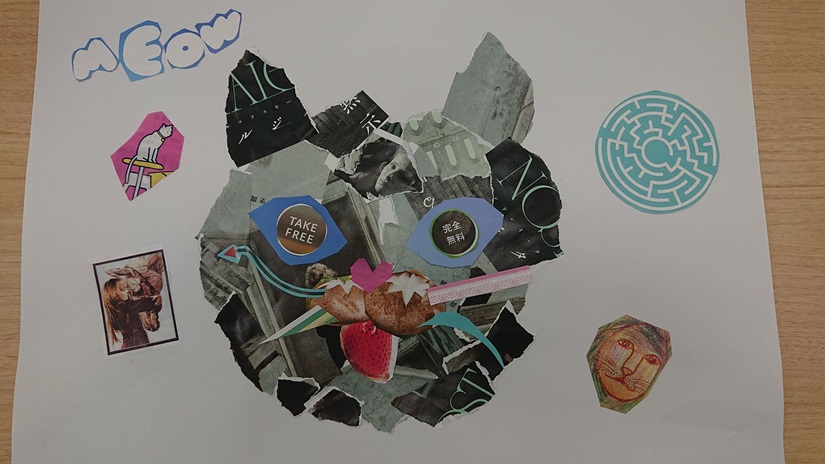

②就労支援PG:ついていけるか、最初は不安でした
ゆるやか就労に参加して2か月ほどたった時、主治医から週4日の午後の就労支援PGに移行することを勧められました。
ゆるやか就労が楽しかったので正直あまり気が進みませんでしたが、
自分としても働くことを考えたらステップアップが必要と思い最終的には就労支援に移行することを決めました。
コミュニケーションについてはある程度ゆるやか就労で自信をつけることはできましたが、
もともと仕事をするためのスキルや知識には自信がなかったため、講座の内容や周りのレベルについていけるかがとても不安でした。
実際に就労支援PGに移行して最初のころはかなり壁を感じました。
特に最初の頃一番大変だったことは、周りの人と自分を比較してしまったことです。
周りには結構頭がいい人もいて、その人と自分を比較して、落ち込んで帰ることも多かったです。
最初は大変ではありましたが、次第に雰囲気にも慣れ、少しずつ落ち着いて自分の力を出せるようになっていきました。
自分の考え方の癖を修正するような講座などのおかげもあり、今は以前ほど比較しなくてすむようになりました。
また学生時代から人前で話すことにはずっと苦手意識がありましたが、講座の中で練習するうちに少しずつ上達して、今ではだいぶ落ち着いて話せるようになりました。
苦手なことも無理のない範囲でチャレンジができる環境がとてもありがたかったです。
③活動が増え、次のステップへ
現実的な働くための次のステップとして、サポステ(※1)にも並行して通っています。
(※1) サポステ
正式名称『地域若者サポートステーション』
働くことに悩みを抱えている15~49歳までの方を対象に、就労に向けた支援と定着支援を行う公的機関。
(※厚生労働省のサポステHPが開きます)
また、「ウォーキングフットボール」という講座に参加したのをきっかけにフットサルサークルにも参加するようになり、活動の範囲が広がったと感じます。


だいぶ働く自信もついてきて視界が開けてきた気がしています。
思えば主治医に言われて仕方なく始めたことでしたが、その繋がりが状況を大きく変え、全く新しい景色が見えてくる。
まずやってみることの大切さを感じています。
はるかぜ就労支援PGに繋がった後のステップ
就労支援PGメンバーのダイです。ここでは、現時点で就労支援PGの利用を検討している方向けの情報コーナーとして、
就労支援PGにつながった後のステップについてお話ししたいと思います。
最終的に就労を目指している方は、就労支援PGに通う生活リズムに慣れてきたら、主治医と相談しながら、今後の就労について考えるステップに進んでいきます。
就職活動をしたり、アルバイトやボランティアから始めてみたり、休職中の方は復職など、その後の就労といっても色々な選択肢がありますが、
ここでは主に就職支援機関を利用しての就職活動について触れたいと思います。

私自身も、現在は別の就職支援機関にメインで通いながら、はるかぜ就労支援PGにも週1で通っています。
これまで色々な所を見学してみた経験からお話しできればと思います。
私は午後の就労支援PGに参加していたので、月〜木曜日の午前中や、休診日の金曜日を活用しやすく、主にその時間で地域の就職支援機関を見学に行っていました。
(見学や体験利用の日程がプログラムと被ってしまう場合は、はるかぜの方をお休みして大丈夫です)
就職支援機関には、ハローワークや就職エージェント、サポステ、就労移行支援事業所(※2)、ジョブカフェ(※3)など様々な所があります。
(※2) 就労移行支援事業所
障害福祉サービスのひとつ。障がいのある方等が、訓練や面談、実習等を通じて適性に合った職場への就労と定着を目指す民間機関。
下記HPの「ココルポート」以外にも、さまざまな事業所があります。
(※3) ジョブカフェ
正式名称『ちば若者キャリアセンター ジョブカフェちば』
15〜39歳までの方(正社員経験の少ない方は44歳まで可)を対象に、就職支援サービスを提供して、正社員等を目指す公的機関。
(※ジョブカフェちばの公式HPが開きます)
私は主にサポステと就労移行支援をいくつか見学しました。それぞれ特色が違うので、余裕があれば何箇所か見学しつつ、自分に合った場所を探すのがオススメです。
(初めての場所に電話で予約を取って見学に行く⋯という事を繰り返すだけでもだいぶ疲れるので、無理なく進めることと自分を褒めるマインドが大切だと思います)
色々と見て回る中で、一人で全て考えるのではなく、就労支援PGの講師に相談して一緒に考えたり、他の選択肢も紹介して頂いたりしながら進められたことや、
就労支援PGの仲間から色々な情報やアドバイスを貰うことができたことが心強かったです。
また、就職活動の段階に進んでも、引き続きはるかぜ就労支援PGとの繋がりがあることも、大きな支えになっています。
ここに来ることで気分転換になったり、第三者目線でアドバイスを貰えたり、「こういう対応をされて困った」等を相談出来たり、はるかぜの皆と話して癒されたりなど、たくさんの良さを感じています。
生きづらさで繋がって その先に繋がっていくということ
就労支援PGの火・水・木を担当しているNPO法人セカンドスペースの降屋(フリヤ)です。
就労支援PGは職場の人間関係や心理的要因など、それぞれの生きづらさや困りごとにより、
働くことを一旦立ち止まってみた休職中の方や働くために一歩踏み出した方が参加しています。
そんな就労支援PGで私が大切にしているのが参加者どうしの繋がりです。
例えば、講座中に皆さんそれぞれの考えや経験をシェアしてもらったり、休憩中のちょっとした雑談だったり、同じ場を共有して繋がっていくこと自体がケアに繋がっていくと考えています。
これは実施団体であるセカンドスペースの『集団で傷付いた心は集団で癒やされる』というスタンスが根底にあります。
精神疾患や生きづらさがなかなか人に言えない時、参加者みんなが同じ状況だからこそ、
初参加時にまずは「そのままの自分で大丈夫ですよ」と受け入れられる場が就労支援PGなのです。
本紙掲載の『生きづらさを語ろうの会』はそんな繋がりの延長線上にあるものです。
いつかは働き始める就労支援の特性上、この場での繋がりは一時的かもしれません。
だからこそ、新たな一歩を踏み出してその先に繋がっていく方々にとって、
少し特殊なご縁で繋がった就労支援PGでの経験が、なにかのプラスになるような場作りを今後も目指していきたいです。
おまけの4コマ漫画

ここまでお読みいただきありがとうございました。
いいねボタンで応援して頂けると励みになります!
はるかぜ通信第7号はこれで完結となります。
別号のはるかぜ通信も随時投稿していきますので、ぜひお楽しみいただけましたら嬉しいです。


